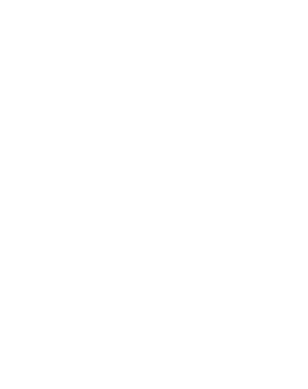
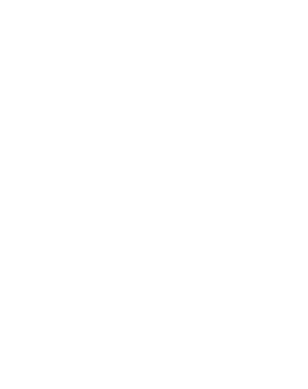
福岡市中央区、福岡PayPayドームやヒルトン福岡シーホークをバックにそびえるベンガラ色の五重塔をご存知でしょうか。
福岡県で初めての木造五重塔「大圓寺五重塔」です。
飛鳥・白鳳時代の伝統が平成の世に生かされ、総高26.5mの高さを誇る、空に向かってそびえる大きなシンボルです。
〒810-0063
福岡県福岡市中央区唐人町3丁目10-9
Tel.092-751-5494
福岡市地下鉄 唐人町駅(4番出口)より徒歩5分
駐車場有 約40台
御参拝時間 午前9時~午後6時
※年間を通して開けております。